『子どもがスポーツの習い事で掛け持ちはあり?』
と気になることありますよね。
我が家の二男は、スポーツの習い事を掛け持ちしたことも影響して小学5年生で腰椎分離症になってしまいました。
まさに、オーバーワーク。
「ジャンルの違うスポーツを掛け持ちすることで身体機能が向上した」という話もありますが、子どもがスポーツの習い事を掛け持ちするリスクも考えておくべきです。
我が家と同じような失敗をしないために、スポーツを掛け持ちする場合、家庭で注意したいことを書いています。是非参考に。
腰椎分離症とはいわゆる背骨の疲労骨折のことです。
腰椎(背骨の下部)の椎弓(ついきゅう)と呼ばれる部分に疲労骨折が生じ、骨が2つに分かれてしまう状態です。成長期のスポーツ選手に多く、繰り返し腰を反らせたり、ひねったりする動作が原因です。進行すると、分離すべり症となり、腰椎がずれて日常生活に支障をきたす恐れもあります。
子どもが習い事で掛け持ちしていたスポーツ
子どもが掛け持ちしたスポーツの習い事は次の通り。
スイミング

年中から週1回、1時間のコースで習っていました。
習得が早く、小学2年生で4泳法でも泳げるようになっていました。2年生(8歳5か月)でクロール50m 47秒。この年代にしては早いタイムです。運動が好きな子どもなので、「このまま続ければ選手に選ばれるかも」なんて期待もしていました。
4年生あたりから急にタイムが遅くなり、本人のやる気が失せてやめることになりました。
野球

スイミングと掛け持ちしたスポーツの習い事は野球。小学1年生から土日だけの野球クラブで習っていました。長男が入会したので、同時期に入会しました。
指導者は平日の自主練を勧めていました。キャッチボールや素振り。低学年も重めのバットでの素振りを勧められていました。
土日の練習では2.5mくらいの長いポールを素振りして遠心力で体がぶれないような練習も、高学年と同じようにしていました。
守備ではショートをしていましたが、腰椎分離症の診断を受ける直前にはショートからファーストへの送球が2バウンドでしか投げられなくなっていました。
今思えば、荷重をかけたトレーニングをしていことがオーバーワークになっていました。そこへスポーツの掛け持ちの習い事が拍車をかけていたと感じます。
短距離走

小学5年生では「野球と短距離走」を掛け持ちしていました。
短距離走のクラブ活動時間はは平日週1回90分です。ずっと走っているのではなく、大きなボールを使って体のバランスを養うトレーニングや、縄跳びや腿上げなどのドリルもしていました。
入会時に掛け持ちのスポーツがあるか聞かれ、オーバーワークに注意を払って指導してくれました。スイミングと野球ではなかったクールダウンもしっかりやるクラブでした。
子どもがスポーツの習い事を掛け持ちして腰椎分離症に
スポーツの習い事を掛け持ちでケガ発覚
ある日、野球練習の帰宅後に子どもがこんなことを言いだしました。

腰が痛い
3、4年生の頃に数回あったように思います。大人でも立ちっぱなしの日は腰が痛くなるものです。次の日は何も言わないので、深く考えていませんでした。
小学5年生の時、野球の試合の次の日、子どもが朝ベットから起きようとした時

腰が痛くて、立てない
尋常ではない痛がり方だったため、その日に整形外科へ行くことに。歩くのも一歩一歩が小さく、すたすた歩けない状態でした。
ケガの診断
触診と問診、レントゲンの結果「腰椎分離症」の疑い。
後日、MRIの結果左側だけの「第5腰椎分離症」末期。6ヶ月以上前に発生して、コルセットで固定しても骨をくっつけることは出来ない状態と言われました。
救いは右側はセーフだったこと。二男は運動が大好きな子どもなので両方の分離症で治らないとなれば、すべり症の危険があるので、運動を思いっきりできないと思っていました。

整形外科の先生から「右側は問題ない」と言われた瞬間、大粒の涙が溢れました。
子どものスポーツの習い事によるケガのメンテナンス

腰椎分離症の末期で、腰椎をくっつける状況にないと判断されたので、コルセットで固めてくっつける治療をしませんでした。
理学療法士の指導のもと次のリハビリをしました。
- 痛みの軽減
- 体幹の可動域改善
- 体幹筋力向上
大人のアスリートとは違って、小学生用に重さを掛けない指導を受け、「痛みが改善したら、ケガの事を理解したうえで野球や好きなスポーツは出来るよ」と言われました。
温存できた右側も腰椎分離しないように体幹を強くするリハビリ指導を受け、スポーツ復帰をめざしました。リハビリ中であっても痛みがない時は有酸素運動はして大丈夫とも言われていました。
ケガ発覚後 掛け持ちしていたスポーツ指導者の対応
野球
腰椎分離症について監督を始め、コーチも初めて聞くとのことでした。地域のクラブだからケガについて深い知識があるとは限らないですね。指導者や他の保護者からこんなことを言われました。
- 段差を歩いてはいけない
- 回転運動をしないバントだけすればいい
- ランナーコーチだけやればいい
こんな的外れなことを言われ、過去にも子どもの体のメンテナンスに気を配っていなかったこともあったので、腰椎分離症の子どもに今後も習い事としてスポーツの指導を受けさせたいとは思えませんでした。
短距離走
短距離走の指導者に「腰椎分離症になりました」とだけ言うと、

スポーツするには腰回りが細すぎる。もっと食べて体幹も強くしないと…
整形外科の理学療法士の方と同じように体幹を鍛えることを言われ、小学生の体に理解のある指導者だとあらためて感じました。
後で気が付きましたが、理学療法士に指導されのと同じ体幹を鍛える補強運動も練習中にしていました。
運動好きな子どもなので、体のケアを含めて信頼してその後も「短距離走」の習い事を続けました。
子どもがスポーツの習い事を掛け持ちする家庭が注意したいこと
整形外科の検査においても腰椎分離症がいつから始まっていたのかは分かりません。実はスイミングで急にタイムが落ちてきた小学校4年生の頃かもしれません。

子どもが重大なケガにならないために、経験した私が思うスポーツの習い事を掛け持ちするご家庭の注意すべきことは次の2つです。
- 子どもの体の痛みに敏感になる
- 子どもの体に理解のある指導者を選ぶ
子どもの体の痛みに敏感になる
子どもが「痛い」と言うことが筋肉痛だからそのうち治る。なんて安易に思わないことです。私はこの点失敗したと思っています。
痛みと体のメカニズムについて少しでも知識があれば重大なケガを防ぐことができます。
成長期の子どもがスポーツする上で、知っておきたい体のメンテナンスについて分かりやすく書かれている本がこちらです。写真が多く、親も子どもも理解しながらスポーツする体のメンテナンスができます。
タイトルが「中高生~」となっていますが、小学生からでも十分参考になる本です。腰椎分離症についても書いてあります。
子どもがケガをしてしまった後ですが、今後も重大なケガにならないために読んでいます。気になった時に、さっと読めるので1冊あると安心です。
腰椎分離症のまま二男ですが、短距離走の習い事だけを続けて、6年生の10月には走り幅跳びで県3位になりました。
「やさしいスポーツハンドブック」と整形外科の理学療法士の方のおかげです。
子どもの体に理解のある指導者を選ぶ
成長期の子どもの体は、骨や関節の成長と筋肉の成長がアンバランス。過度な負荷による疲労が重大なケガになるリスクになります。
子どもの体やメンテナンスについて知識のある指導者のもとでスポーツの習い事をすることがおすすめです。オーバーワークにも気を配ってくれるはずです。
指導者に体のメンテナンスの知識があるか判断する良い方法は、クールダウン(整理運動)もしっかり指導しているかどうか。スポーツの技術だけでなく、メンテナンスも重視している証拠です。
子どもがスポーツの習い事を掛け持ちで失敗しないために・・・

私の子どもはスポーツの掛け持ちで腰椎分離症といった重大なケガになりました。考えられる要因は次の通りです。
- 掛け持ちしたことで体に疲労があった
- 子どもの体やメンテナンスに知識の浅い指導者だった
- 親が子どもの体の痛みに敏感でなかった
子どもがスポーツを掛け持ちすることで良い結果を得ている場合もあります。ご家庭では子どもの体のメンテナンス知識をつけて、ケガなく思いっきりスポーツを楽しめる体つくりを心がけて下さい。
計算学習の習い事として小学生に人気のくもんとそろばん。どっちがいいのか、こちらを参考に。
【計算力を鍛える くもんvsそろばん】
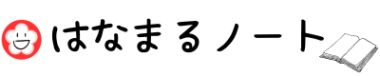
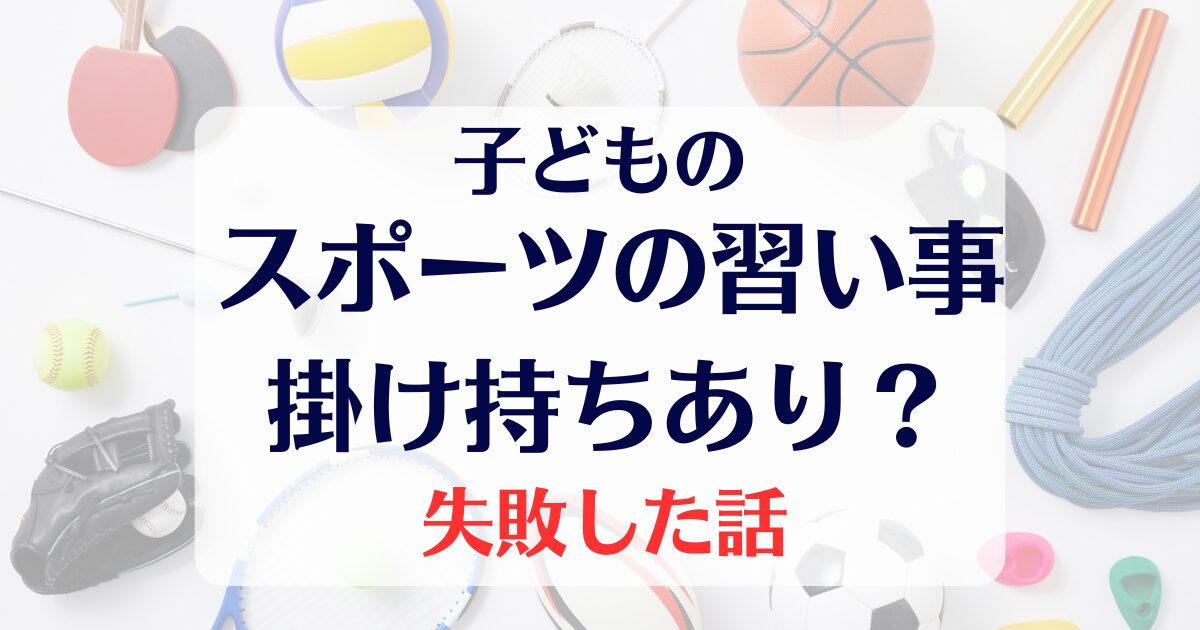


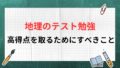
コメント